この記事はアフィリエイト広告を含みます。
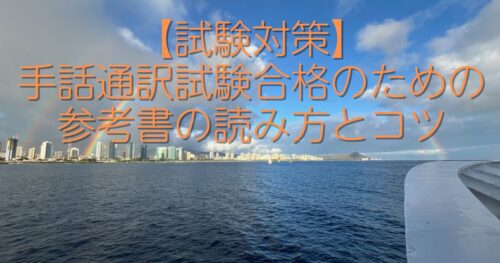
こんにちは。
手話通訳者として活動する中で、
多くの方から「試験勉強のコツを教えてほしい」というご質問をいただきます。
今回は、手話通訳士試験や統一試験に向けた参考書の効果的な読み方について詳しくお伝えします。
目次
試験勉強をはじめる前に
新年度になり、そろそろ受験勉強を始めようと考えている方も多いのではないでしょうか。
手話通訳士試験も統一試験も参考図書が指定されていますが、
その内容の難しさに驚いて、なかなか手を付けられないという方もいらっしゃると思います。
しかし、自分に知識がない以上は参考図書や過去問題を頼りに進めるしかありません。
ここでは、専門的な参考書を上手に読むためのアドバイスをご紹介します。
自分に当てはまるところを参考にしてください。
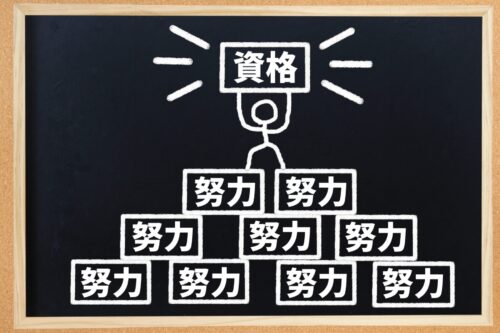
参考書選びのポイント
手話通訳試験の参考図書はかなりの数になります。
ではすべての参考図書が必要なのでしょうか?
これは受験勉強をスタートしたタイミングによっても変わってきます。
時間とお金の兼ね合い
- 時間に余裕がある場合:多くの参考図書に目を通す時間があるでしょう
- 3ヶ月程度の短期間で勉強する場合:すべての参考図書を読むことは困難です
参考図書をたくさん買い揃えるには費用がかかり、また自宅のスペースも必要となります。
こうしたデメリットを考慮した上で、本当に自分に必要な参考図書を選ぶことが重要です。
おすすめの選び方
- 余裕がある人: まず参考図書を一通り読み、その後過去問題に取り組む。理解が足りない部分は再度参考図書で確認する方法がおすすめです。
- 時間に余裕がない人: まず過去問題を数年分解いてみて、自分が苦手だと思うジャンルを把握してから、その分野に関する参考図書を購入するという方法も効率的です。

効率的な参考書の読み方
参考書には読み方のコツがあります。例えば、
手話通訳士試験の参考図書である「手話通訳技能認定試験傾向と対策 手話通訳試験合格への道(七訂)」を例に見てみましょう。
STEP1: 導入部分をしっかり読む
目次の前にある「学ぶにあたって」という文章や、
試験案内、各設問についての説明など、
最初に書かれている文章は本の目的や概要が記されているので、必ず読むようにしましょう。
STEP2: 目次を通読する
目次を全て読むことで、取り組むべき全体像が見えてきます。
また、各章ごとに「傾向と対策」が書かれているので、
これも必ず目を通しましょう。
それぞれの課題ごとのイメージをつかむことがとても大切です。
STEP3: マーキングと付箋の活用
参考書のすべての文章を何度も読み返すのは時間がかかります。
時間を短縮するためにも、参考書には惜しみなくマーカーを引くことをおすすめします。
また、特に重要なページや何度も見返したい部分には付箋を貼りましょう。
何度やっても解けない問題には特別な色の付箋を貼るなど、工夫すると効率的です。
過去問題の活用法
過去問題は試験対策の要です。
情報文化センターの手話通訳士試験関係のホームページに掲載されている過去問題は
解答の解説まではついておらず、過去3年分程度しかありません。

過去問の入手方法
より多くの過去問や解説が欲しい場合は、
過去問題集を購入することをおすすめします。
最低でも過去5年分、理想的にはそれ以上の過去問題を揃えるとよいでしょう。
インプットとアウトプットのバランス
- 参考図書で勉強する = インプット
- 過去問題を解く = アウトプット
自分が記憶した情報を過去問題を解くことで脳の中の引き出しから取り出して利用する作業、
それがアウトプットです。その結果、記憶がしっかりと定着していきます。
過去問を解く際のコツ
過去問題と同じページに回答が書いてある場合、
どうしても目に入ってしまいがちです。
私自身の経験では、全ての回答に付箋を貼って見えないようにし、
必要な時だけ付箋をめくって確認していました。
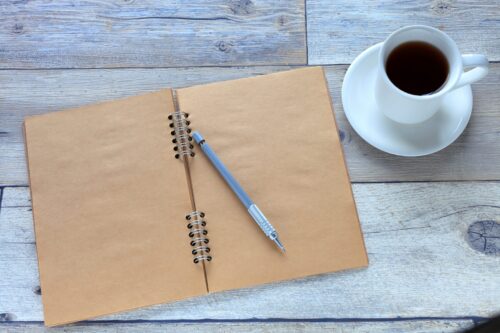
効果的なノートの取り方
ノートは何のために書くのか、自分なりにルール作りをすることが大事です。
「書く」という行為は覚えやすく忘れにくい記憶法なのでおすすめします。
ノートの目的を明確に
- 復習用のノート: 後で読み返せるようなノートを書くことで、膨大な文章を毎回読み返す手間が省けます。
- 記憶用の書き込み: 年代や人名を記憶する場合は、きれいなノートよりも、メモ用紙などに何度も書いて記憶する方が効果的です。
書く目的に合わせて、使い分ける感覚も必要でしょう。

勉強のモチベーション維持法
毎日勉強を進めていると、どうしてもやる気が起きない日が出てきます。
そんな時は思い切って勉強をやめて気分転換するのも一つの方法です。
勉強の調整方法
集中力が続かないと感じるタイミングが分かるようになったら、
それが試験本番や直前にならないように調整しましょう。
また、理解できない問題に過度にこだわらず、一旦置いておくことも時間短縮になります。
合格基準を意識する
試験には合格基準があるので、どうしても理解できない問題があったとしても、
他の問題で点数を取れれば合格できます。
完璧を求めすぎずに、効率的な学習を心がけましょう。
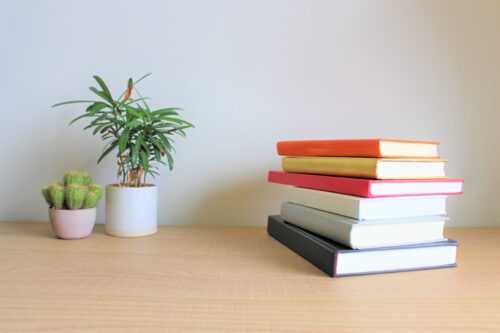
まとめ
手話通訳士試験や統一試験の勉強は、参考書の効果的な活用と過去問題の繰り返し学習がカギとなります。
試験勉強は決して楽な道のりではありませんが、
正しい方法で取り組めば、必ず成果につながります。
- 自分の状況に合った参考書を選ぶ
- 参考書は最初の導入部分から丁寧に読む
- マーカーや付箋を活用して効率的に復習
- 過去問題でアウトプットを意識する
- 目的に合わせたノート術で記憶を定着
- 無理せず、メリハリのある勉強計画を立てる
これらのポイントを意識して、ぜひ効果的な試験勉強を進めてください。
皆さんの合格を心から応援しています!