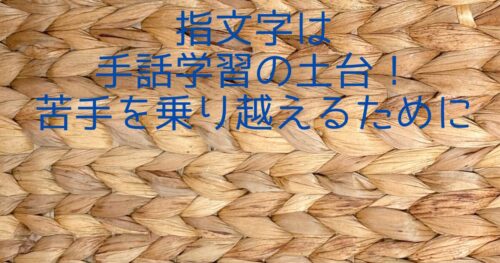この記事はアフィリエイト広告を含みます。
手話の世界へようこそ。
手話を学ぶうえで、指文字の役割はとても大きなものです。
アルファベットや数字、カタカナなどを手の形で表す指文字は、日常のやりとりに欠かせない重要なツールです。
聴覚障害のある方々との円滑なコミュニケーションだけでなく、手話通訳者としての実践力にも直結します。
このブログでは、そんな指文字について、基本から応用までを丁寧に深掘りしていきます。
また、手話学習に関する関連記事として、
-
「手話単語」
-
「口形と表現」
-
「手話とイメージ」
-
「手話のフレーム」
-
「目線の使い方」
といったテーマにも触れていきます。
学びに終わりはありません。一緒に、一歩ずつ理解を深めていきましょう。

指文字が苦手なあなたへ
「指文字、どうしても苦手なんです」
そう話す学習者の声をよく耳にします。
それは受講生だけでなく、実際に現場で活動している手話通訳者にも多い悩みです。
たとえば、あるろう者からこう言われたことがあります。
「あなたたち(聴者)の指文字は下手なんだから、
はっきり、ゆっくりやってくれないと、こっちはわからないんだよ」
この言葉が、ずっと心に残っています。
私たちはつい、聴こえた日本語のテンポでそのまま指文字を出してしまいがちです。
特に「却下(きゃっか)」や「アップデート」といった拗音を含む言葉は、焦ってしまう場面もあります。
でも、指文字はテンポより「確実に伝えること」が大切です。
たとえば、「っ」はしっかり指文字の形をつくり、少し後ろに引いて表現してみましょう。
「きゃりーぱみゅぱみゅ」なんて、指文字の練習にはぴったりの言葉かもしれません。

コツは「毎日ちょっとだけ」練習すること
指文字の上達には、日々の積み重ねが効果的です。
たとえば駅のホームで電車を待っている時間に、目に入った看板や広告の文字を指文字で表してみる。
そういった「小さなアウトプット」の積み重ねが、自然と自信へとつながっていきます。
指文字を上達させるためのポイントは、以下の4つです:
-
相手から見やすい位置と角度で
-
はっきりと、丁寧に
-
焦らず落ち着いて
-
そして毎日の練習を欠かさずに

最後に
手話学習は一人ひとりのペースで進めてよいものです。
指文字に苦手意識を持っていても、焦らず、まずは「ゆっくり、はっきり」と意識するだけでも変化が見えてきます。
手話通訳者として、そして手話を学ぶ一人として、学びはずっと続いていきます。
このブログが、あなたの学びに少しでも役立てば幸いです。
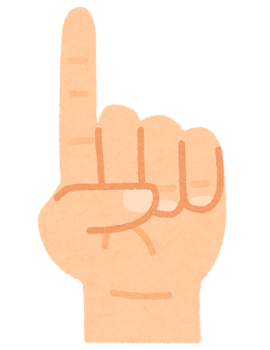
あとがき
聞こえない方の中には
指文字が苦手な方もいらっしゃいます。
どう表せばいいのか困ったときに
指文字を「つい」使ってしまいがちですが
ほかにどんな方法があるか
(生活で使う範囲の手話で説明できるか)
考えることも大切です。