この記事はアフィリエイト広告を含みます。
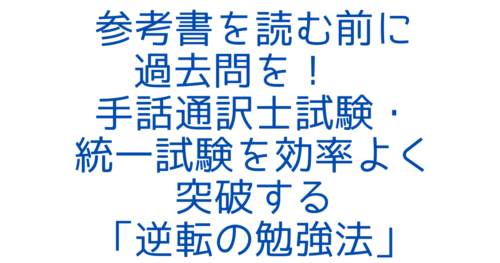
手話通訳士試験や全国統一試験を目指して勉強中のみなさんへ。
「参考書ばかり読んでいて、時間が足りない」
「過去問をやらずに試験日が近づいてしまった」
そんなこと、ありませんか?
勉強には順番があります。
そして「読むだけ」では合格できないのが、この試験の特徴でもあります。
大切なのは「使える知識」
参考書は知識を頭に入れるもの(インプット)。
過去問はその知識を引き出して使うもの(アウトプット)。
試験本番で問われるのは、**どれだけ知識を思い出して使えるか**です。
✔ 知っているつもりだったけど答えられなかった
✔ 問題文の意味がつかめなかった。
そんな悔しい経験は、アウトプット不足のサインかもしれません。

過去問→参考書の順でOK!
時間に限りがあるなら、まずは過去問から。
そして、わからなかった部分をピンポイントで参考書で補う。
この「逆転の勉強法」が、じつは最も効率的です。
* 数年分の過去問をざっくり解いてみる
* 苦手ジャンルを見極める
* 必要な参考書だけにしぼって読み直す
この流れなら、無駄がなく、知識が定着しやすいです。
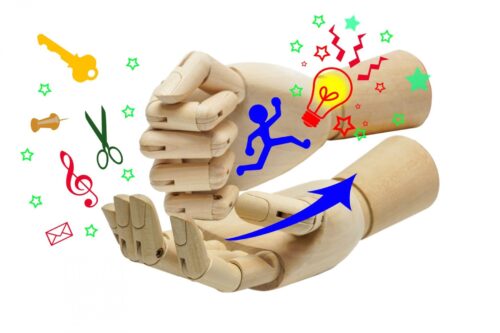
参考書の全部読みは非効率かも?
手話通訳士試験には、数多くの参考書が存在します。
でも、それらをすべて丁寧に読むのは至難の業。
そこでおすすめなのがこちら:
* イメージがわかない科目だけ、目次と「はじめに」だけでも読んでおく
* ろう運動など背景を知る科目は、全通研の記念誌などで補強すると◎
「読まなきゃ…」という焦りは、**優先順位で整理する**だけで、ぐっとラクになります。
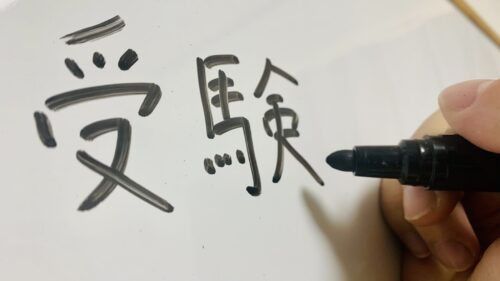
インプット3:アウトプット7の法則
よく「インプット7:アウトプット3」が一般的と言われますが、
実際にはインプット3:アウトプット7の方が、記憶の定着率が高いとも言われます。
* アウトプットが多い人ほど、試験本番で強い
* 繰り返すことで、引き出す力がついていく
* 問題を解くたびに「記憶の引き出し」が整理されていく
知識は、使ってこそ身につくのです。

読解力も立派な「攻略スキル」
私はかつて、国語の読解が苦手でした。
ですが試験対策の一環として読解力を鍛えた結果、
* 法律や福祉などの難しい文章も理解しやすくなった
* 正解の根拠が文章内から見つけられるようになった
文章読解の力は、あらゆる科目に通じる万能スキルです。
読解に苦手意識のある方は、ここから取り組んでみるのもおすすめです。

最後に
結果を変えるには、やり方を変えること
同じやり方を続けていても、結果はなかなか変わりません。
やり方を変えれば、見える世界が変わります。
合格の先にある「現場で役立つ通訳力」を身につけるために、
いまの勉強を前向きに、効率よく進めていきましょう。
私のnoteの記事を紹介します
手話通訳士試験、筆記試験の勉強に役立つ。苦手な過去問題を分析するテンプレートとアドバイス。私はこれで合格できた。
聞き取り通訳で差がつく!実技試験を突破する練習法と評価基準の完全ガイド
手話通訳士試験対策|聞き取り力を鍛える7場面 × 音声3速付き教材