この記事はアフィリエイト広告を含みます。
※この記事は日本財団ジャーナルに掲載された内容を元に作成しています。
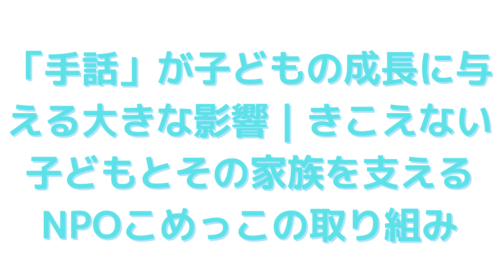
きこえない・きこえにくい子どもとその家族にとって、「手話」はどのような意味を持つのでしょうか?
今回は、日本財団ジャーナルに掲載された記事から、
きこえない・きこえにくい子どもたちの言語発達と心の成長を支援する
NPO法人「こめっこ」の活動についてご紹介します。
手話言語の早期習得が子どもの成長に与える影響と、
それを科学的に証明する画期的な研究プロジェクトについてお伝えします。

目次
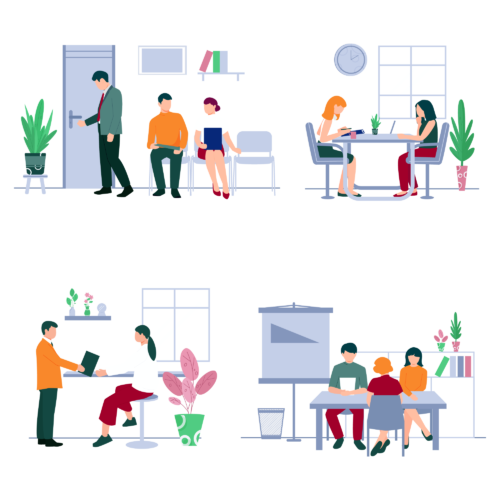
きこえない子どもたちが直面する課題
出産後、自分の子どもがきこえない・きこえにくいと判明したとき、
多くの親御さんは「どうにかきこえるようにならないか」と苦心します。
その結果、言語発達の遅れや、コミュニケーション不全など、
子どもたちは成長過程でさまざまな困難に直面することがあります。
NPO法人こめっこの常務理事である久保沢寛さんは、きこえない当事者として次のように語ります。
「きこえない子どもの立場としては、やはり親が手話で話してくれると安心します。
音声優位の社会のなかで、きこえない人たちは情報を得るために常に気を張らなくてはいけません。
でも、それは負担が大きい。だからこそ、家庭内に手話があるとホッとしますし、
気を張る必要がない、という安心感にもつながるのではないでしょうか。」

手話獲得が子どもの発達に与える影響
こめっこのスーパーバイザーである神戸大学の河﨑佳子教授は、
臨床心理学の観点から、親子間のコミュニケーションが子どもの発達に与える影響について言及しています。
「赤ちゃんは親と触れ合うことで自然と言葉を身につけていくもの。
親はそれを見て『かわいいね』『すごいね』と笑顔になる。
そんな親とのやりとりを重ねて、子どもたちは『ぼくでいいんだ、私でいいんだ』
と自己肯定感を育みながら成長していくんです。」
特に0歳から3歳までの期間が、子どもの発達において非常に重要だと河﨑教授は強調します。
この時期に適切な言語環境、つまりきこえない・きこえにくい子どもにとっては手話を提供することで、
健全な人格形成や心の発達を促すことができるのです。
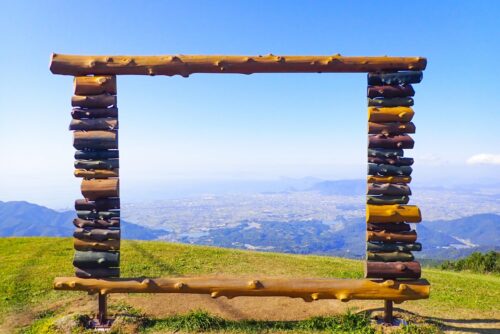
「手話言語を獲得・習得する子どもの力研究プロジェクト」とは
こめっこでは、日本財団の助成を受けて
2020年から「手話言語を獲得・習得する子どもの力研究プロジェクト」を進めています。
このプロジェクトは、乳幼児期からの手話獲得・習得が
子どもの発達にどのような影響を与えるかを科学的に証明するものです。
研究は以下の4つの分野から進められています:
- 脳科学: 手話が言語として脳の言語領域を活性化することを証明
- 心理発達: 情緒、認知、コミュニケーションなど複数の側面からの発達調査
- 言語獲得(手話・日本語): 手話と日本語の力を定量的に測定
- 学習能力(理解・思考): 手話による理解力や思考力の発達を調査
この研究を通じて、きこえない・きこえにくい子どもたちにとって手話がいかに重要な言語であるかを示し、
最終的には学習指導要領に手話を言語として認めた教育を織り込むことを目標としています。

親御さんたちの声
こめっこに通う親子からは、多くの前向きな変化が報告されています。
あるお母さんは、子どもの耳がきこえないと分かった時の混乱から、
手話を覚えていく我が子を見て変化した心境を語ります:
「子どもが手話を少しずつ覚えていくのを見て、
『この子、手話なら分かるんだ!』と素直にびっくりしました。
それからどんどん手話が伸びていって、ちゃんとコミュニケーションが取れるようになった時に、
私自身にも『手話で生きていくことを応援しよう』という気持ちの変化があったんです。」
また別のお母さんは、こめっこで出会ったきこえないスタッフたちをロールモデルとして、
子どもの将来への不安が解消されたことを話しています:
「私は聴覚障害と他の障害がごっちゃになってしまって、
『この子は将来、ひとりで生きていけるんだろうか』と思い込んでいました。
でも、こめっこのスタッフさんたちを見て、それが間違いだったんだと気付きました。
たとえ耳がきこえなくても、自立して生きていけるんだと思えるようになりました。」

こめっこが目指す未来
こめっこの代表理事である物井明子さんは、親御さんの支援も重要だと語ります:
「0歳から3歳までの期間が本当に大切であることを実感しました。
パパやママがハッピーだと、子どももハッピーになれる。
そう信じて、みんなが幸せになれる支援をしていきます。」
河﨑教授は最終的な目標として、
きこえない・きこえにくい子どもがいつでも受け入れられる保育園の設立を挙げ、こう締めくくっています:
「そこで育った子どもたちには自然とインクルージョンな感覚が身につきますし、
そういう子どもたちが成長していけば、インクルーシブな社会ができあがると信じているんです。」
私たちにできることは、手話を言語として理解し、尊重すること。
きこえない・きこえにくい人たちに日本語を押し付けるのではなく、
手話を広めていくことで共生していく。
そんな姿勢こそが、誰ひとり取り残さない社会の実現に必要なのかもしれません。
NPO法人こめっこの活動について、詳しくは公式サイトをご覧ください。
※この記事は日本財団ジャーナルに掲載された内容を元に作成しています。