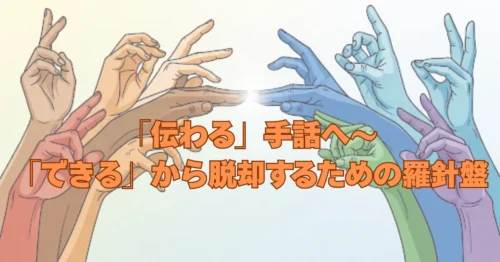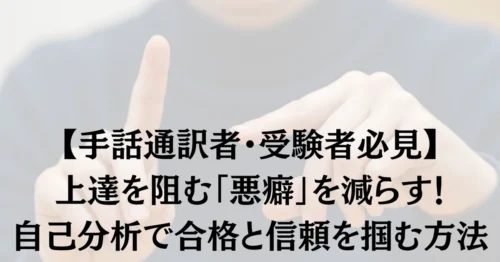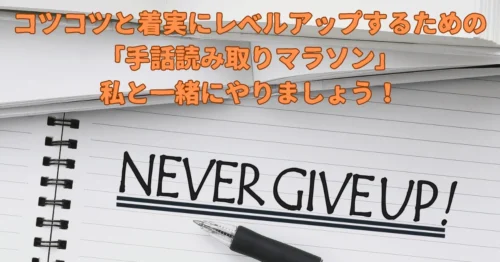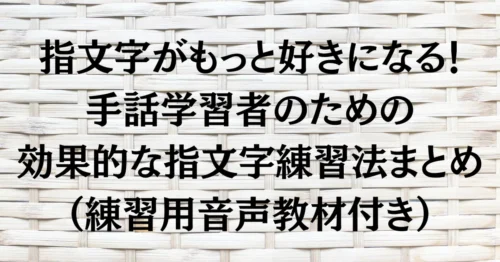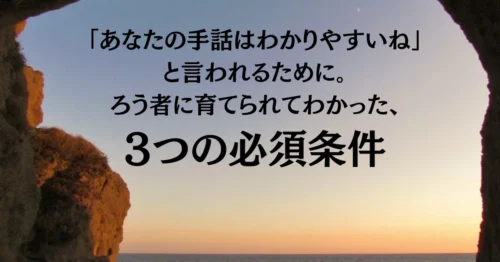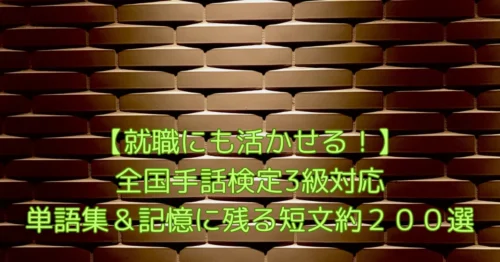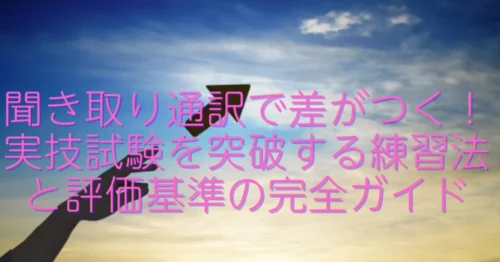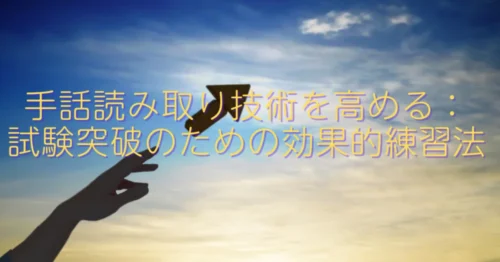私のnoteの記事にはいくつかの種類があります。
・無料記事
・有料記事
・メンバー限定記事
その中の手話学習、試験突破に役立つ有料記事からいくつか紹介します。
それぞれの記事は「効果がない」と思った際に全額返金するようになっています。
一度お試しください。
今がそのタイミング!読解力を身に着けて手話学習を飛躍的に向上させよう
あなたの「伸び悩み」の原因はここにある
単語は知っている。文法も学んだ。それなのに、なぜ「会話」が続かないのか?
手話通訳者、あるいは手話学習者であるあなたは、今、こんな壁にぶつかっていませんか?
-
「テキストで覚えた手話の単語はたくさんあるのに、ろう者の話す『生きた手話』になると、なぜか意味を取り違えてしまう…」
-
「手話の表現自体は合っているはずなのに、ろう者との会話で、どうも『心と心が通じ合っている』実感が持てない…」
-
「通訳の現場で、聞いた手話をそのまま日本語に訳したら、話の意図が抜け落ちてしまい、『結局、何を言いたかったの?』と聞かれてしまった…」
この悩みは、あなたが手話に真剣に向き合っている証拠です。単語や文法を一生懸命学んだ努力は、決して無駄ではありません。しかし、残念ながら、その努力が「真のコミュニケーション」に結びついていないのには、決定的な理由があります。
それは、あなたが手話学習において最も重要な「ある力」を見落としているからです。
その力とは、「読解力」です。
「手話学習の罠」:暗記だけでは絶対に超えられない壁
あなたは、これまでどれくらいの時間を手話の単語帳や文法書、表現集に費やしてきましたか?
私たちはつい、外国語を学ぶのと同じように、「手話も、単語をたくさん覚え、文法を理解すれば話せるようになる」と思い込みがちです。しかし、これが手話学習者が陥りがちな「単語学習の罠」です。
なぜなら、手話通訳やろう者との円滑なコミュニケーションの現場で求められるのは、単なる「言語の置き換え」ではないからです。
ろう者の手話は、指の動きや形だけでなく、表情、視線、体の動き、そしてその場の文脈といった、極めて多くの情報が詰まった「ビジュアルコミュニケーション」です。
あなたは、相手が発した一つの手話表現を見て、「ああ、これは『〇〇』という意味だな」と理解するだけでは十分ではありません。その表現の『奥』にあるものを読み解く必要があります。
その「奥」とは、こういうことです。
-
「意図」: この人は、この表現を使って、最終的に何を伝えたいのか?(単なる事実か、意見か、感情の吐露か、要望か?)
-
「背景」: この手話が生まれた文脈、文化的・社会的な背景は何か?(その人自身の経験、手話独特の言い回し、時代背景など)
-
「感情」: 表情や動作の強さから見て、この言葉にどのような感情的なニュアンスが込められているか?(喜びの度合い、不満の深さ、皮肉の有無など)
これらを総合的に、一瞬で、正確に理解し、そして適切な日本語や手話に「再構築(リフレーミング)」する力こそが、手話における真のコミュニケーション能力です。そして、この「意図」「背景」「感情」を読み解く力こそが、まさに「読解力」の正体なのです。
単語をたくさん知っているだけでは、あなたはいつまで経っても、手話の森で「木」しか見ていない状態から抜け出せません。必要なのは、「森全体」を見通すための、高次元の思考ツール、すなわち「読解力」という名の「地図」です。
読解力があなたの手話に「飛躍的な成長」をもたらす
手話通訳士として活動する中で、私は多くの学習者や受験生を見てきました。そして、「伸びる人」と「伸び悩む人」を分ける決定的な違いは、この「読解力」にあると確信しています。
「読解力」と聞くと、難しい書籍を読む力だと誤解されがちです。しかし、ここでいう「読解力」とは、ビジネス書ベストセラーで語られるように、「物事の本質や意図を瞬時に読み解く、最強の思考ツール」です。
この力を手話学習に取り入れることで、あなたの手話は劇的に変わります。
あなたは、この有料記事を読むことで、以下の未来を手に入れます。
-
ろう者の発言の「真意」を、単語レベルではなく、「メッセージ全体」として把握できるようになり、「会話が噛み合わない」という不安から解放されます。
-
通訳の現場で、単なる「言葉の変換機」ではなく、「話し手の心に寄り添い、正確に意図を伝える通訳者」として信頼を得られるようになります。
-
手話の練習や学習が、単なる暗記作業ではなくなり、「知的で楽しい探求活動」へと変わります。
もう、単語帳をひたすらめくるだけの学習は終わりにしましょう。
本記事では、手話通訳士の視点から、「読解力」がなぜ手話に必須なのかを理論的に解説し、さらに明日からすぐに実践できる具体的なトレーニング方法を、【実践ワーク】として徹底的に掘り下げます。
「読解力」という最強の武器を手に、あなたの手話学習を「飛躍的な向上」へと導きましょう。
記事を読んでみたい方は以下の画像をクリック
「伝わる」手話へ〜「できる」から脱却するための羅針盤
手話学習者の皆さん、こんにちは。
今回は、私自身の経験を交えながら、手話における「できる」と「伝わる」の違いについて、そして「伝わる」手話を実現するために必要な考え方について、深く掘り下げてお伝えしたいと思います。
手話学習の道のりを歩む中で、誰もが一度はぶつかる壁や感じる疑問について、一緒に考えていきましょう。
「聞き取り」と「読み取り」の狭間で試行錯誤する日々
手話の実技練習には、大きく分けて二つの要素があります。
一つは、聞こえてきた日本語を、その意味やニュアンスまで汲み取って手話で表現する**「聞き取り」。
もう一つは、ろう者の手話を正確に読み取り、日本語に翻訳して伝える「読み取り」**です。
私たちは、学習者の第一言語である日本語と、日々懸命に学んでいる手話という二つの言語を、自分の頭の中にある膨大な「引き出し」から瞬時に選び出し、駆使します。
この二つのスキルを磨くことは、手話コミュニケーションの基礎であり、スムーズな表現の第一歩となります。
手話通訳は、基本的に同時通訳という非常に高度なスキルを要します。
話者が日本語を話している間、その内容を「受容」しながら、記憶に留め、「翻訳」を同時進行で行い、そして「表出」する。さらに、手話で表現しながらも、相手の表情や反応を読み取ったり、次に話される内容に耳を傾けたりと、複数の思考プロセスを同時にこなすという、まさに「離れ業」をやってのけるのです。
手話講習会では、この「受容〜表出」の一連の流れを教わりますが、そのすべてが「○○しながら」の状態になっているため、初学者がこれを習得するのは容易なことではありません。
記事を読んでみたい方は以下の画像をクリック
【手話通訳者・受験者必見】上達を阻む「悪癖」を減らす!自己分析で合格と信頼を掴む方法
「なぜか評価されない」を卒業!手話通訳の「悪癖」を直し、飛躍的に上達する自己分析法
手話通訳者、手話学習者、そしてこれから試験に挑もうとしている皆さん。
一生懸命に手話を学んでいるのに、なかなか上達を実感できない。
試験に挑んでも、なぜか不合格になってしまう。
講師や先輩に指摘されなければ、自分の何が悪いのかわからない。
その悩み、実は「努力が足りない」からではありません。
もしかしたら、あなた自身も気づいていない「悪癖(あくへき)」が、あなたの成長を阻んでいるのかもしれません。
この有料記事では、あなたが自分の手話表現を客観的に見つめ直し、上達を阻む「悪癖」に気づくための具体的な視点を手に入れることができます。
そして、加点を増やす練習に加えて、減点を減らすという新たな学習法を学ぶことで、確実に実力を伸ばしていくためのセルフチェック方法を知ることができます。
この記事を読めば、あなたは自分の悪癖に気づき、改善する手助けを得られます。
そして、その過程を自己評価していくために、定期的に録音・録画を行うことが必須です。
さあ、あなたのパフォーマンスを上げるための「悪癖」の改善法を、一緒に見ていきましょう。
記事を読んでみたい方は以下の画像をクリック
コツコツと着実にレベルアップするための「手話読み取りマラソン」私と一緒にやりましょう!(あらかわいおりの読み取り音声、解説付)
手話の読み取り、なかなか上達しなくて行き詰っていませんか?
短期間で上達が難しいのが読み取りです。
でも、上達したいですよね。試験に合格したいですよね。
手話の実技の勉強法のコツは、
-
イベント的な盛り上がりで、一時的に長時間集中して、その後やらないようなムラのあるやり方はダメ。
-
感情の起伏を利用しないで、毎日の生活と同じテンションで、淡々とやる。
-
段差の浅い階段を上っていると思うこと。淡々とやることで、いつか高いところにたどり着ける。
-
読み取りをやるうえでの約束事を必ず実行すること(後述します)
この読み取りマラソンでやっていくこと
-
読み取りの教材が18あります。それぞれを3日ずつ練習します。私が先行してやっていきますので、同じペースでついてきてください。自分のタイミングとペースで進んでいただいて結構ですが、休まないようにしてください。
-
この記事を私が日々更新していきます。最終的には18×3=54日でゴールします。(手話通訳士試験実技試験に役立ててほしい気持ちがあります)
-
私もやってみる!と思った方は、日本通訳士協会のDVD「読み取ってみよう&表現してみよう2024」を各自用意してください。
-
わたしも毎回実行して記事を更新して、映像付きの読み取り音声をアップしていきます。
毎回必ずやってほしいこと
-
読み取りは必ず声を出して行ってください。できたかどうかより、声を出すことが先です。
-
読めなくてもあきらめずに続けてください。あきらめない気持ちは大切です。
-
毎回自分の読み取りを録音してください。できればスマホで読み取り動画を録画しながら読み取ってください。そうすると、映像と比較して読み取りを自己評価できます。それを自分で聞く、見るようにしてください。
-
ノートに簡単な記録をつけるとなお良いです。18問あるので各3回として「1-1」初見、何とか全部読めた。声が小さくなってしまった。など、簡単に記録しましょう。
-
うまくいかないときは、その日の練習時間を増やすか、練習日数を増やしてください。毎回の課題はあきらめることなくクリアしていきましょう。
やってはいけないこと
皆さんの様子をわたしが見ることができませんので、一般的な「それはダメですよ」ということを列挙しておきます。それを参考に、自己評価してください。
-
声が小さい。自信がなくなると語尾が聞こえなくなる。
-
自信がない時に語尾が上がって疑問形にしてしまう。
-
読める単語を言うだけで文章になっていない。
課題の進め方
一つの課題を全3回で考えています。声を出す。録音するのは毎回です。毎回の練習時間は短くていいです。15~30分もやれば十分です。毎日コツコツやることが重要です。
1回目
-
初見で読み取る
-
単語が読み取れない場合は参考文を読む
-
手話のスピードについていけない場合は再生速度を下げる
-
もう一度読み取る
2回目
-
読み取る
-
手話をシャドーイングする。速さについていけないときは再生速度を下げる。シャドーイングできない単語は意味を知らないということです。完全にシャドーイングできるまでやる。
-
読み取る
3回目
-
今までの自己評価で反省点を克服できるように読み取る
以上の繰り返しです。
私に質問があるときは、この記事にコメントしてください。お答えします。
では、始めましょう。
記事を読んでみたい方は以下の画像をクリック
指文字がもっと好きになる!手話学習者のための効果的な指文字練習法まとめ(練習用音声教材付き)
こんにちは。手話を学んでいる皆さん、「指文字を覚えるのが難しい」「だんだん単調に感じてきた…」そんな悩み、ありませんか?
今回は、楽しく・確実に・日常に取り入れやすい指文字練習法を、たっぷりご紹介します。初心者さんも独学派も、ぜひ今日から試してみてください。
1. ランダム練習で“即レス力”を鍛える
順番通りの「あいうえお」練習は基礎固めに最適。でも、実際の会話では文字はランダムに現れますよね。
だからこそ、「ランダムで指文字を表現する」練習が超重要!
「あなたの手話はわかりやすいね」と言われるために。ろう者に育てられてわかった、3つの必須条件
「あなたの手話、すごくわかりやすいですね」
そう言われた瞬間、胸がじんわり温かくなったことがあります。
でも——。
その言葉をもらえるようになるまで、私は長い時間をかけて育てられ、試され、たくさんの“わからなさ”と向き合ってきました。
私は手話講習会に通い始めた頃から、あるろう者の団体に見込まれ、できもしないのに通訳を「やらされ」るようになりました。
今なら感謝しかありませんが、当時は何度もくじけそうになったことを覚えています。
「あの手話、何言ってんの?」
初めて通訳の現場に入ったとき、ろう者の方が隣の人にこう言いました。
「あの手話、何言ってんの?」
顔をしかめ、眉間にしわを寄せ、まるでパズルのピースがまったくはまらないような顔で私を見ていたのです。
そこから私の手話通訳は、毎年のように評価が変わっていきました。
-
1年目:顔をしかめられる。ささやかれる。
-
2年目:無表情。反応が見えず、ただただ不安。
-
3年目:わずかに頷き。理解されたかどうか不確か。
-
4年目:「やっと、わかるようになったな」と苦笑い。
-
5年目:自然な表情、自然な頷き。話のリズムが合う。
この5段階を超えて、ようやく「通訳できている」と言えるようになりました。
それまで何を変えたのか?
どんな練習をしたのか?
この記事では、「わかりやすい手話通訳」に必要な3つの条件を丁寧にお伝えします。
記事を読んでみたい方は以下の画像をクリック
【就職にも活かせる!】全国手話検定3級対応:単語集&記憶に残る短文約200選「音声データ付き」
〜「使える手話」を目指す、実践型トレーニング集〜
この記事では、全国手話検定3級を目指す皆さんのために、
-
必須単語集(出題頻度の高いものを網羅)
-
その単語を使った短文約200本
-
効果的な覚え方・参考辞典・NHKアプリの使い方
をまとめています。
単語と短文の読み上げた音声データを付けました。
音声に合わせて表現練習ができます。
◆ 全国手話検定3級ってどんなレベル?
-
日常生活・社会生活での会話を想定した内容
-
初対面のろう者とも自然な会話が成立するレベル
-
履歴書に書ける技能資格として認知されている
-
一般就職・福祉関係・接客などでもアピール材料に!
◆ このnoteの構成
✅ 全国手話検定3級でよく出る単語集(分野別)
✅ その単語を使った「自然な短文」300本
✅ 各短文は文法・語順を考慮した会話形式
✅ NHK「手話CG」アプリや辞典を使った記憶術も紹介
記事を読んでみたい方は以下の画像をクリック
聞き取り通訳で差がつく!実技試験を突破する練習法と評価基準の完全ガイド
手話通訳士試験や全国手話通訳者統一試験を受験される方へ。
特に実技試験の中でも「聞き取り通訳」は多くの方にとって大きな壁となります。
本記事では、試験に出る評価基準をもとに、どこを意識して練習すれば合格に近づくのかを詳しく解説します。
手話通訳士試験だけでなく、統一試験受験者にも活かせる内容です。
私の記事:手話通訳士試験対策|聞き取り力を鍛える7場面 × 音声3速付き教材
も、併せて活用してください
手話読み取り技術を高める:試験突破のための効果的練習法
手話通訳士試験・全国手話統一試験に挑戦するあなたへ
かつて手話関係の本で読み取りの練習法が書かれたものを見たことがありません。
講習や研修を受けても具体的な練習法を教わったことがないという方も多いのではないでしょうか。
それほどに読み取りの練習法を言語化したものがなかったのです。
私が各所で読み取りの研修をすると、一様に「初めて聞いた」という感想が帰ってきます。
そこで今回、私の実践的なノウハウを紹介することにしました。
この有料記事を購入したあなたが効果を認めない場合は遠慮なく返金手続きをしてください。
この記事を購入いただくことで、長年の手話通訳経験と試験対策の指導から導き出した「読み取り」のための効果的な練習法を手に入れることができます。
多くの受験者が最大の壁と感じる「読み取り」の技術を向上させるための具体的な方法論を提示し、
どこで躓きやすいのか、どう克服すべきかを詳細に解説します。
この記事のアドバイスを実践することで、以下のメリットが得られます:
-
効率的な自宅学習法で短期間での実力アップが可能に
-
DVDなどの教材を最大限に活用するノウハウが身につく
-
試験に直結する実践的な読み取り能力の獲得
-
現場でも役立つ確かな技術の習得
-
効果的な練習を繰り返すことで、自信を持って試験に臨める
それでは具体的な内容に入りましょう。
記事を読んでみたい方は以下の画像をクリック
私、あらかわいおりのメンバーシップです。メンバー限定の情報をお届けします。
私の著書です。手話の勉強法を身につけましょう。
私のnoteの有料記事がお得に読めるマガジンです。