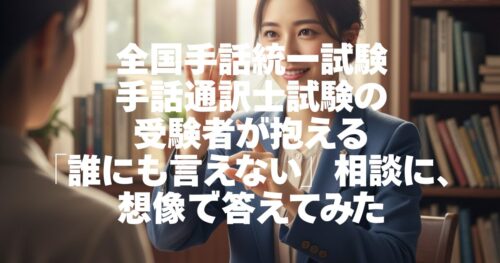
はじめに
手話通訳士の荒川いおりです。手話学習や手話通訳に関わる情報を発信しています。
今回は、手話通訳士試験や全国手話統一試験を目指す皆さんが、心の中で抱えながらも「誰に相談したらいいかわからない」「こんなこと聞いたら怒られるかな」と思ってしまうような、孤独な悩みや疑問に、私なりの言葉で想像し、お答えしていきたいと思います。
私自身、手話通訳士試験に挑戦し、不合格の泥沼に足を踏み入れた経験があります。その中で感じた「正解がどこにあるかわからない」という感覚は、今でも鮮明に覚えています。
受験生時代、私たちは多かれ少なかれ、同じような孤独を抱えながら学習を進めているのではないでしょうか。この記事が、皆さんの心に少しでも寄り添い、前に進むためのヒントになれば嬉しいです。
1.学習方法・技術に関する相談
これは一見、先生やサークルの先輩に聞けそうですが、実は「その人には聞けない」という微妙な壁があることが多いものです。
Q1: 「正しい」手話とは何ですか?方言や個人差にどこまで対応すべき?
これは永遠のテーマですよね。学習者の方々から、「教わった手話と、ろう者の友人の手話が違う」「地域によって形が全然違う。試験ではどれを使えばいいの?」といった不安をよく聞きます。
荒川の想像と回答:
あなたが抱える不安、非常によく理解できます。「正しい手話」なんて、実は存在しません。手話は生きている言語であり、方言、世代差、個人差、そして文脈によって常に変化します。
試験で求められる「手話」は、「自然で、流暢で、誤解なく、かつ幅広いろう者に理解される表現」です。つまり、「試験委員が理解できる、最も普遍性の高い手話」を習得する必要がある、と言い換えることができます。
-
学習の基本は、やはり『手話奉仕員養成講座』や『手話通訳者養成講座』で教わる、「標準的な手話」です。まずはこの型を徹底的に体に染み込ませましょう。
-
その上で、多様なろう者との交流を通じて、「この表現はこういう言い方もするのか」と引き出しを増やしていくことが重要です。試験の読み取り対策としては、「自分が習った表現ではないけど、何を言っているか理解できる」訓練が最も大切になります。
-
通訳・表現対策としては、「表現の普遍性」を意識してください。特定の地域やコミュニティだけで通用する表現は、極力避け、できるだけ多くのろう者に伝わる(=試験委員に伝わる)表現を選ぶ努力が必要です。
Q2: 毎日どれくらい学習すればいいのか?仕事との両立が辛い。
特に社会人受験生にとって、この悩みは深刻です。学習時間が足りない焦り、そして学習が進まない自己嫌悪に陥りがちです。
荒川の想像と回答:
「理想は毎日〇時間!」と言いたいところですが、現実的には不可能です。無理をして燃え尽きるのが一番怖いです。
大切なのは、「継続性」と「質」です。
-
時間より「質」: 1日5時間、ただダラダラと過去問を眺めるより、30分集中して、自分の苦手な分野(例えば、専門用語の表現、数字の表現など)を徹底的に反復練習する方が、はるかに効果があります。
-
スキマ時間を活用: 通勤中の電車の中、昼休みなど、「移動・音声なし」の時間こそ、手話の復習に最適です。過去の通訳練習の動画を頭の中でリプレイしたりする時間にあてましょう。
-
ルーティン化: 「毎日寝る前に15分だけ動画を読み取る」など、「これだけは必ずやる」というミニマムなルーティンを設定してください。達成感が自己肯定感につながり、継続の原動力になります。
-
誰にも相談できない「辛い」気持ちは、「合格したい」という真摯な気持ちの裏返しです。自分を責めないでください。「今日は頑張った」と、小さな自分を褒めてあげてください。
2.精神面・モチベーションに関する相談
実技試験は、まさにメンタルとの闘いです。この種の悩みは、受験仲間にもなかなか打ち明けにくい、個人的な「弱さ」に関わることなので、特に孤独になりがちです。
Q3: 実技試験で頭が真っ白になるのが怖くて、練習でも力が出せません。
「人前で通訳する」という行為は、極度の緊張を伴います。特に試験となると、そのプレッシャーは計り知れません。
荒川の想像と回答:
「頭が真っ白になる」というのは、脳が「逃走・闘争反応」を起こしている状態です。これは人間の本能的な防衛反応なので、あなたが弱いわけではありません。
この不安を乗り越えるには、「慣れ」と「準備」しかありません。
-
「失敗の練習」をする: 練習会やサークルで、「今日はあえて、一番難しい表現に挑戦して、失敗してみよう」とテーマを決めてみてください。完璧を目指すのではなく、「失敗しても、次の表現にどう繋げるか」というリカバリー能力を磨く練習です。失敗しても命は取られません。この「失敗しても大丈夫」という経験が、本番のプレッシャーを軽減します。
-
「完璧主義」を手放す: 試験は「完璧に通訳できる人を選ぶ」のではなく、「通訳者として一定のレベルに達している人を選ぶ」ためのものです。多少の間違いは、合否に直接影響しません。重要なのは、「メッセージの核心」を伝えることです。
Q4: 不合格が続いて、周りの合格者から取り残されていく焦りが辛い。もう諦めた方がいいのか?
これが、最も深刻で、最も誰にも言えない悩みでしょう。合格した仲間のキラキラしたSNSの投稿を見るたびに、胸が痛む。その気持ち、痛いほどわかります。
荒川の想像と回答:
まず言わせてください。あなたは、決して「取り残されている」わけではありません。
資格試験の合否は、あなたの手話能力のすべてを測るものではありません。そして、手話学習という道のりにおいて、他人と自分を比較することほど、意味のないことはありません。
-
「同期」ではなく「同志」を見る: 合格した仲間は、あなたのライバルではなく、先に山を登り終えた同志です。彼らが合格できたノウハウは、必ずあなたの役に立ちます。嫉妬や焦りではなく、「どうやって合格できたのか」を尋ねる勇気を持ちましょう。
-
試験を受ける「意味」を再確認する: なぜあなたは手話通訳士になりたいのですか?「周りが受かったから」ですか?違いますよね。「ろう者の役に立ちたい」「通訳のプロになりたい」という、あなた自身の内なる動機を、もう一度しっかり思い出してください。
-
諦めるのは簡単です。しかし、これまで費やしてきた時間、労力、そして何より「手話通訳士になりたい」という熱い想いは、どこへ行ってしまうのでしょうか。
-
「休む」ことと「諦める」ことは違います。もし心が疲弊しきっているなら、試験勉強を一時的に「休む」ことを検討してください。手話通訳の現場から離れる必要はありません。ただ、試験というプレッシャーから離れ、純粋に手話やろう文化を楽しむ時間にしましょう。そして、「もう一度頑張れる」と思った時、試験勉強を再開すれば良いのです。
3.実務・倫理に関する、素朴な疑問
試験合格後を見据えた、学習者ならではの純粋な疑問。これも、先生や現役通訳士には「そんなことも知らないの?」と思われそうで聞きにくいものです。
Q5: 試験合格後にすぐに現場で通用するのだろうか?現場と試験のギャップが怖い。
資格を取っても、それがそのまま仕事に直結するのか。これは多くの受験生が抱える不安です。
荒川の想像と回答:
結論から言えば、資格を取っただけでは、プロの現場で通用しません。
しかし、それは当たり前のことです。運転免許を取得したばかりの人が、すぐにF1ドライバーになれないのと同じです。
-
試験合格=「プロのスタートライン」: 手話通訳士試験の合格は、「この人はプロとして必要な最低限の知識と技術を持っている」という証明に過ぎません。ここからが、プロとしての本当の学びの始まりです。
-
ギャップは埋められる: 現場の通訳は、試験のように「原稿ありき」ではありません。予測不能な発言、文脈、専門性、そして何より「人間関係」が加わります。
-
このギャップを埋めるためには、まず「奉仕員」として地域の派遣事業で経験を積むことです。
-
そして、研修会に積極的に参加し、「試験対策」ではなく「現場対策」の技術を学ぶ必要があります。
-
合格は、あなたの不安を裏付けるものではなく、あなたの未来を切り拓くパスポートです。試験対策で培った努力を、今度は現場での経験に変えていきましょう。
おわりに:あなたは一人じゃない
手話通訳士試験も全国手話統一試験も、孤独な闘いです。
誰にも言えない悩み、胸の奥にしまい込んだ不安。
それでも、あなたがその試験に挑む理由は、きっと「誰かの役に立ちたい」という、とても美しく、尊い想いからきているはずです。
もし、この記事を読んで、少しでも心が軽くなったり、「そうか、このやり方でいいんだ」と思えたりしたなら、私としては嬉しい限りです。
あなたは一人ではありません。
この孤独な道の先には、手話通訳士という、尊い職業が待っています。
どうか、自分を信じて、もう一歩だけ前に進んでみてください。
私も、応援しています。
#手話通訳士試験 #全国手話統一試験 #手話通訳 #手話学習 #受験対策 #メンタルケア #手話の勉強法 #資格試験の悩み #誰にも言えない悩み
私が直接オンラインで指導するココナラの紹介です。楽しく優しくアドバイスします。
今月中やっているメンバーシップのメンバー限定でオンラインであなたを無料アドバイスする企画です。
私、あらかわいおりのメンバーシップです。メンバー限定の情報をお届けします。
私の著書です。手話の勉強法を身につけましょう。
私のnoteの有料記事がお得に読めるマガジンです。