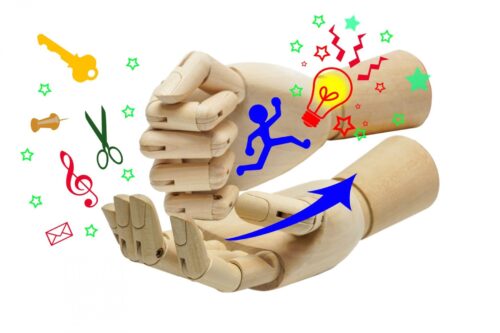この記事はアフィリエイト広告を含みます。
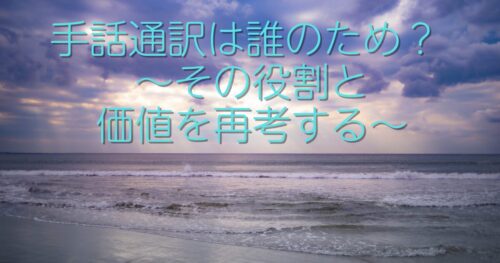
こんにちは、手話学習者や手話通訳者の皆さん。
今日は「手話通訳は誰のため?」という根本的な問いについて、深く考えてみたいと思います。
思い込みを問い直す
手話を学ぶ私たちは、「手話通訳は誰のためか」と問われると、
多くの人が「聞こえない人のため」と即答するでしょう。
もちろんそれは間違いではありません。
しかし、それだけなのでしょうか?
実は手話通訳の役割と価値は、もっと広い視点から捉える必要があると感じています。
一緒に考えてみましょう。

医療現場から見える真実
医療現場の例を考えてみましょう。
聞こえない方が病院を訪れるとき、どのような流れになるでしょうか。
まず受付を済ませ、定期検診なら様々な検査を受けることになります。
採血、採尿、超音波検査、X線撮影...それぞれの検査室を回り、
最終的に医師の診察を受けます。
そして会計を済ませ、処方箋があれば薬局へ向かいます。
この一連の流れの中で、医療事務、検査技師、医師、薬剤師など、
様々な医療関係者とのコミュニケーションが発生します。
手話通訳者はそれらのコミュニケーションを円滑につなぐ役割を担っています。
確かにこれは聞こえない方のためのサポートですが、
同時に「サービスを提供する側」の医療関係者のためでもあるのです。
手話通訳者が介在することによって、医療関係者は正確な情報を患者さんに伝え、
また患者さんから正確な情報を得ることができるのです。

現場から学んだ教訓
私の経験から一つお話しします。
ある大きな病院で聞こえない方の検査に同行した際のことです。
検査技師に「手話通訳者です。必要なことがあればやり取りを通訳します」と伝えたところ、
「必要ありません。私が筆談でやりとりしますので外で待っていてください」と言われました。
聞こえない方にその旨を伝えると「筆談でやり取りするので外で待っていていいよ」とのことでした。
しかし結果的に検査は通常の時間を大幅に超過し、
検査後に出てきた検査技師は申し訳なさそうに
「大変時間がかかって申し訳ありませんでした」と言っていました。
医療現場はどこも患者さんで溢れ、待ち時間の長さが問題になっています。
手話通訳者がいることで正確かつスムーズなやり取りができることは、
実は医療関係者にとっても大きな恩恵なのです。
時間が節約できますし、誤解によるリスクも減らせます。

コミュニティ通訳という概念
「コミュニティ通訳」という言葉をご存知でしょうか?
手話通訳士試験では必須の学習項目ですね。
司法通訳や会議通訳といった専門的な通訳ジャンルと異なり、
日常生活に直結する通訳業務を総称して「コミュニティ通訳」と呼んでいます。
医療現場での通訳もこれに含まれます。

通訳の価値と報酬の矛盾
少し話は逸れますが、国際政治の場面を想像してみてください。
アメリカの大統領と日本の総理大臣がトップ会談をしている時、
背後には必ず通訳者がいますよね。
また各国の代表団による交渉の場にも通訳者は必ず配置されています。
こうした業務を担当する通訳者は、非常に高額な報酬を得ています。
なぜでしょうか?
取り扱う内容が難しいから?
会話する人たちがハイレベルだから?
もし社会的地位の高い人の会話に対する通訳の対価が高いのなら、
医師だって十分に社会的地位は高いはずです。
しかし、医師と聞こえない方のやり取りをつなぐ手話通訳者の報酬は、
残念ながら非常に低いままです。
極端な例を挙げれば、アメリカ大統領と日本の総理大臣のやり取りを担当する通訳者は高額な報酬を得られるのに対し、
日本の総理大臣と聴覚障害者団体のやり取りを手話通訳者が担当したとしても、
日常業務と同程度の報酬しか得られないでしょう。
この矛盾を言葉で説明できますか?
これは、一方の社会的地位が低いとみなされることで、
通訳業務自体の価値も低く見積もられてしまう風潮があるということです。

障害の社会モデルから考える
障害について学んだことがある方なら、
「医学モデル」と「社会モデル」という考え方をご存知でしょう。
社会的地位を基準にした考え方は、障害の社会モデルの観点からも問題があります。
改めて問いかけます。
手話通訳は誰のため? 何のため?
障害を社会モデルで捉えると、社会の仕組み自体が障害を作り出していると考えます。
社会的地位が低いとか、少数派だといった理由で人が大切にされないのは、
非常に悲しいことではないでしょうか。

未来への展望
このような状況が見直され、社会が変わっていけば、
手話通訳を含めたコミュニティ通訳はより認知され、身分が保証され、
収入も向上するでしょう。
そうなれば、この道を目指す若い人も増えていくはずです。
手話通訳者の専門性の必要性や、手話通訳を学ぶ大学の必要性を主張する声があることは承知しています。
しかし、専門性を持った手話通訳者が現場で活躍することを本当に望むなら、
手話通訳者がしっかりとした身分保障を得られるように制度を充実させなければなりません。
そうでなければ、それは「絵に描いた餅」に過ぎません。
コンビニのアルバイトよりも不安定な収入環境で「専門性を持った手話通訳者になってください」と言っても、
担い手が増えるとは思えません。
実際、手話通訳を学ぶ大学は増えず、
専門学校は定員割れして手話学科が次々と閉鎖されている現状があります。

共に考える未来
「誰のために、何のために」という問いをきちんと考えていくならば、
行政も企業も一般の人々も、手話通訳の本当の価値と役割について正しい認識を持つことが必要です。
手話通訳は「聞こえない人のため」であると同時に、「聞こえる人のため」でもあり、
そして「社会全体のため」でもあるのです。
コミュニケーションの橋渡しをすることで、より多くの人が社会に参加でき、
多様性が尊重される社会づくりに貢献しているのです。
私たち手話学習者・手話通訳者は、自分の役割の価値を再認識し、
誇りを持って活動していきましょう。
そして社会に対しては、その価値を適切に評価してもらえるよう、
声を上げ続けることも大切ではないでしょうか。
皆さんはどう思いますか? 一緒に考え、より良い未来を創っていきましょう。