この記事はアフィリエイト広告を含みます。
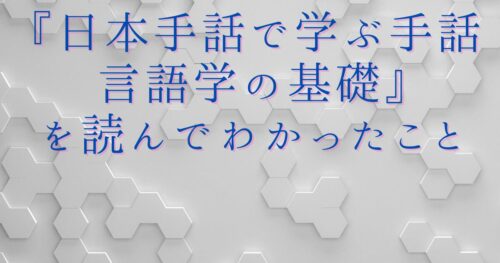
―手話通訳士試験に向けて、今だからこそ学びたい―
手話通訳の研修を担当することになり、『日本手話で学ぶ手話言語学の基礎』を改めて読み返しています。
この本は、手話通訳士試験の参考図書にもなっている重要な一冊です。
● 試験対策としては必読
この本からは実際に多くの出題があります。
講師目線で読むと「ここからどこを出題されてもおかしくない」と思えるほど、試験問題が作りやすい内容です。
つまり、受験生にとっては「ここを覚えておけば得点源になる」ありがたい一冊でもあるのです。
● 現役通訳者や指導者にもおすすめ
この本に書かれている内容は、現在活躍中の通訳者の方々が学んでこなかったであろう「手話言語学の基礎知識」が詰まっています。
経験だけでは補えない理論的な裏付けを学ぶことで、現場での通訳に自信と説得力が増します。
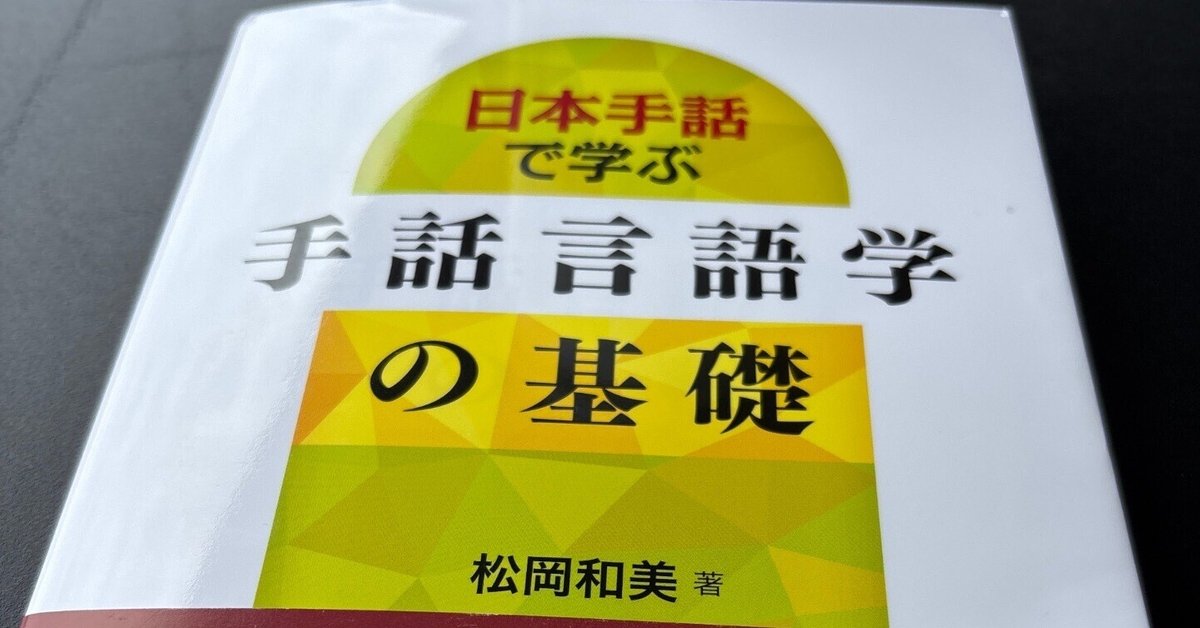
どんな内容なのか? ざっくり目次紹介
-
第1章:手話の音韻
-
第2章:手話の形態
-
第3章:手話の統語
-
第4章:意味に関わる手話言語の性質
-
第5章:CL・RS・手話の創造性
-
第6章:ろう児の手話の発達
特に注目したいのが「両手を使う手話とバチソンの制約」の項目です。
ここでは「対称性の条件」「利き手に関する制約」など、これまでなんとなく理解していたことを明確に説明してくれます。
例えば――
・両手が同じ手形なら、動きは同じか交互である(対称性の条件)
・両手手話で利き手が動く場合、非利き手は“無標手型”でなければならない(利き手に関する制約)
「そんなの昔からそうでしょ?」
と感じるかもしれませんが、それを言葉で説明し、誰かに伝えられるかがポイントです。

学び直しのきっかけになる
自分では理解していたつもりでも、いざ誰かに教えるとなると、言葉に詰まってしまう。
そういった“知っているつもり”の壁を、この本は取り払ってくれます。
私のように、「言葉にできないことが多い」と自覚している人にとっては、
まさに「考える手間を減らしてくれる」ありがたい一冊です。

バチソンの制約、こんな疑問を考えてみては?
「ノーマライゼーション」という手話。
両手の形は同じだけど、動いているのは利き手だけ。
――これは“制約違反”なの? 例外? それとも?
・新しい手話だからルールが変わってきたのか
・よく見ると非利き手は“無標手型”に該当しているのか
こういった視点で、手話をもう一度見直すチャンスにもなります。
学問とは、過去の研究をベースに積み上げていくもの。
手話言語学も、これからさらに進化していくはずです。

最後に
私たちが手話通訳士試験を目指す理由、あるいは手話通訳という仕事に向き合う姿勢――
それをもう一度考えるうえでも、この本は良いきっかけになります。
合格のためだけでなく、
「なぜこの通訳表現をするのか」
「なぜこの手話が成立するのか」
を言葉で説明できるようになるために。
ぜひ、手に取ってじっくり読んでみてください。
そして、心の中でこうつぶやいてください。
「読んでよかった」と。
こちらからAmazonで購入できます
私のnoteの記事を紹介します
手話通訳士試験、筆記試験の勉強に役立つ。苦手な過去問題を分析するテンプレートとアドバイス。私はこれで合格できた。
聞き取り通訳で差がつく!実技試験を突破する練習法と評価基準の完全ガイド
手話通訳士試験対策|聞き取り力を鍛える7場面 × 音声3速付き教材